名フィル第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2015年12月12日(土) ― 2015年12月17日 05時30分
久々に、名フィルの定期を聴いてきました。
第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ
・ホルスト: 日本組曲 作品33
・藤倉大(名フィル コンポーザー・イン・レジデンス):
フルート協奏曲*[委嘱新作・オーケストラ版 世界初演]
・ホルスト: 組曲『惑星』作品32**
マーティン・ブラビンズ(指揮/名フィル常任指揮者)
クレア・チェイス* (フルート)
愛知県立芸術大学女声合唱団** (女声合唱)
第430回定期演奏会「日本民謡の昇華」~「メタ」シリーズ
・ホルスト: 日本組曲 作品33
・藤倉大(名フィル コンポーザー・イン・レジデンス):
フルート協奏曲*[委嘱新作・オーケストラ版 世界初演]
・ホルスト: 組曲『惑星』作品32**
マーティン・ブラビンズ(指揮/名フィル常任指揮者)
クレア・チェイス* (フルート)
愛知県立芸術大学女声合唱団** (女声合唱)
「4管編成オーケストラ」「パイプ・オルガン」「女性合唱団(しかも終曲のみ)」が要求される、ホルストの「惑星」はなかなか実演で聴く機会が無い・・・ので、聴きに行った次第。金曜日は仕事の都合で行けなかったが、土曜定期はなんとか・・・
ホルストの「日本組曲」・・・ま、確かに「和風」の旋律が洋風の味付け(オーケストレーション)で聴けますなあ・・・という類の組曲。定期の解説(コラム)によると、伊藤道郎との邂逅から生まれた組曲だそうで、このコラムはなかなか読み応えがあった。前菜にはちょうどいいんじゃないかな・・・
フルート組曲・・・う~ん、どうなんでしょ。初っ端から尺八のような激しい息遣いの音を連発されて面食らってしまった。激しさと静けさのコントラストで聴かせる・・・のかねえ・・・クレア・チェイスの「奮闘」は賞賛に値する(十字架のような馬鹿でかいフルートにはタマゲタ・・・)が・・・ま、私の「好み」じゃあないねえ・・・しかし、これは「クラシック音楽」なのか「現代の音楽」なのか・・・というのは私にとってはどうでも良くて、聴いて「感動するか」「感動しないか」だけなのよねえ・・・そういう評価軸からすると・・・音楽と社会の関わりとは何ぞや・・・ですなあ・・・
後半はお待ちかねの「惑星」、ブラスにもっとパワーが欲しい所だが、名フィルは健闘してますなあ・・・やはり実演で聴くと面白い。パイプ・オルガンについてはいつも感じるが、オーケストラの音にかき消されて目立つべき部分が聴き取り難い箇所(土星のペダル・ノートとか、天王星のグリッサンドとか)がやはり・・・オーケストラを圧倒する音が欲しい箇所でも絶対的な「音量不足」は否めない。こればかりは容易に解決出来ないから難しいねえ。SRによるブーストや電子オルガンによる付加を考えたほうが良いのではないだろうか・・・この点は「録音」で聴くのが良いというケースでもある。
ちなみに、今回の席は3階席の中央より後ろ側のA席。メイン・コンソールで弾いているオルガンの様子は良く見えるが、音がオケに負けて聴き取り難い・・・ティンパニの音は良く飛んでくる・・・席によっては、オルガンの音が明瞭に聴こえるかもしれないが・・・難しいですなあ・・・
ま、細かいところを論うと切りが無いので・・・なんにせよ、惑星は久々にオーケストラの醍醐味を楽しめて、実に爽快。難しい評論は評論家にお任せして「音楽は楽しむに如かず」でいきたいものですな。
ちなみに、普通舞台に登場しない「女声合唱団」、今回は演奏後に舞台に登場していた。ブラヴィンズさん、気遣いの人ですなあ・・・
今回のコンサート、「プレ・コンサート」「ポストリュード」は時間の都合で聴けず、ちと残念・・・んでは。
ホルストの「日本組曲」・・・ま、確かに「和風」の旋律が洋風の味付け(オーケストレーション)で聴けますなあ・・・という類の組曲。定期の解説(コラム)によると、伊藤道郎との邂逅から生まれた組曲だそうで、このコラムはなかなか読み応えがあった。前菜にはちょうどいいんじゃないかな・・・
フルート組曲・・・う~ん、どうなんでしょ。初っ端から尺八のような激しい息遣いの音を連発されて面食らってしまった。激しさと静けさのコントラストで聴かせる・・・のかねえ・・・クレア・チェイスの「奮闘」は賞賛に値する(十字架のような馬鹿でかいフルートにはタマゲタ・・・)が・・・ま、私の「好み」じゃあないねえ・・・しかし、これは「クラシック音楽」なのか「現代の音楽」なのか・・・というのは私にとってはどうでも良くて、聴いて「感動するか」「感動しないか」だけなのよねえ・・・そういう評価軸からすると・・・音楽と社会の関わりとは何ぞや・・・ですなあ・・・
後半はお待ちかねの「惑星」、ブラスにもっとパワーが欲しい所だが、名フィルは健闘してますなあ・・・やはり実演で聴くと面白い。パイプ・オルガンについてはいつも感じるが、オーケストラの音にかき消されて目立つべき部分が聴き取り難い箇所(土星のペダル・ノートとか、天王星のグリッサンドとか)がやはり・・・オーケストラを圧倒する音が欲しい箇所でも絶対的な「音量不足」は否めない。こればかりは容易に解決出来ないから難しいねえ。SRによるブーストや電子オルガンによる付加を考えたほうが良いのではないだろうか・・・この点は「録音」で聴くのが良いというケースでもある。
ちなみに、今回の席は3階席の中央より後ろ側のA席。メイン・コンソールで弾いているオルガンの様子は良く見えるが、音がオケに負けて聴き取り難い・・・ティンパニの音は良く飛んでくる・・・席によっては、オルガンの音が明瞭に聴こえるかもしれないが・・・難しいですなあ・・・
ま、細かいところを論うと切りが無いので・・・なんにせよ、惑星は久々にオーケストラの醍醐味を楽しめて、実に爽快。難しい評論は評論家にお任せして「音楽は楽しむに如かず」でいきたいものですな。
ちなみに、普通舞台に登場しない「女声合唱団」、今回は演奏後に舞台に登場していた。ブラヴィンズさん、気遣いの人ですなあ・・・
今回のコンサート、「プレ・コンサート」「ポストリュード」は時間の都合で聴けず、ちと残念・・・んでは。
2012年9月28日(金) 京都市交響楽団 第3回名古屋公演 @愛知県芸術劇場コンサートホール ― 2012年09月29日 09時16分
昨日、京響してきました・・・
京都市交響楽団 第3回名古屋公演
2012年9月28日(金)6:45pm 開演
愛知県芸術劇場コンサートホール
コープランド:バレエ音楽「ロデオ」から、「カウボーイの休日」
ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー *
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調op.27
広上 淳一指揮、京都市交響楽団
*山下 洋輔(ピアノ)
昨日は休みを取って、たっぷり昼寝(&昼に一杯やって)してから行ったので、プログラムの途中で寝ることもなかった・・・仕事後のコンサートは疲れで寝てしまうことが多いのだが・・・
ただ、コンサート開演ギリギリに駆け込んだので、プログラムは頂けたが団員名簿等の別紙は品切れ(?)で頂けなかったのは残念・・・ま、しゃーない・・・次回はもっと早く行こうか・・・
食前酒?のコープランド、もっとパンチを聴かせて粗野な感じがあってもエエんでは?とも思ったが、上品な京風?な仕上がり。これはこれでなかなかいい。
お次の前菜?ラプソディー・イン・ブルー、こりゃ、山下 洋輔のピアノソロ・リサイタルのオマケにガーシュインがくっついていた感じ・・・彼のソロを堪能出来て良かった。勿論、オケも良かったがね・・・う~ん・・・久しぶりにジャズのライブを聴きたくなったぜ・・・
メイン・ディッシュのラフ2・・・やるじゃん!京響・・・3楽章は至福の時であった・・・
京都市交響楽団 第4回名古屋公演 は来年9月13日(月・祝)予定だそうな・・・また聴きに行こう・・・
コンサートの後、大須 くつろぎ食堂Amiで一杯やってたら、同じく大須にある中古オーディオショップのスタッフさんが晩飯食っていて合流・・・久しぶりにオーディオ談義をして楽しい夜を過ごした・・・んでは。
京都市交響楽団 第3回名古屋公演
2012年9月28日(金)6:45pm 開演
愛知県芸術劇場コンサートホール
コープランド:バレエ音楽「ロデオ」から、「カウボーイの休日」
ガーシュウィン:ラプソディー・イン・ブルー *
ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調op.27
広上 淳一指揮、京都市交響楽団
*山下 洋輔(ピアノ)
昨日は休みを取って、たっぷり昼寝(&昼に一杯やって)してから行ったので、プログラムの途中で寝ることもなかった・・・仕事後のコンサートは疲れで寝てしまうことが多いのだが・・・
ただ、コンサート開演ギリギリに駆け込んだので、プログラムは頂けたが団員名簿等の別紙は品切れ(?)で頂けなかったのは残念・・・ま、しゃーない・・・次回はもっと早く行こうか・・・
食前酒?のコープランド、もっとパンチを聴かせて粗野な感じがあってもエエんでは?とも思ったが、上品な京風?な仕上がり。これはこれでなかなかいい。
お次の前菜?ラプソディー・イン・ブルー、こりゃ、山下 洋輔のピアノソロ・リサイタルのオマケにガーシュインがくっついていた感じ・・・彼のソロを堪能出来て良かった。勿論、オケも良かったがね・・・う~ん・・・久しぶりにジャズのライブを聴きたくなったぜ・・・
メイン・ディッシュのラフ2・・・やるじゃん!京響・・・3楽章は至福の時であった・・・
京都市交響楽団 第4回名古屋公演 は来年9月13日(月・祝)予定だそうな・・・また聴きに行こう・・・
コンサートの後、大須 くつろぎ食堂Amiで一杯やってたら、同じく大須にある中古オーディオショップのスタッフさんが晩飯食っていて合流・・・久しぶりにオーディオ談義をして楽しい夜を過ごした・・・んでは。
2012年7月20日(金) コバケン・スペシャル ファイナル(Vol.24) ― 2012年07月21日 07時55分
昨日、後半だけ聴いた 2012年7月20日(金) コバケン・スペシャル ファイナル(Vol.24) のことをチラリと・・・
<ベートーヴェン・セレクションIII >
ベートーヴェン: ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61*
ベートーヴェン: 交響曲第6番ヘ長調 作品68『田園』
小林研一郎 (指揮/桂冠指揮者)
有希 マヌエラ・ヤンケ* (ヴァイオリン)
ホントはキンカンの後に行くつもりだったのだが、結局ケッキンカンになってしまい、コンサートも前半のヴァイオリン協奏曲は聴き逃し、後半の「田園」のみを聴いた・・・

休憩中のコンサート・ホールオルガン&P席の様子・・・
1階席、舞台目の前の1列目、ヴィオラ・セクション一番後ろの真ん前という席。だから、普段良く座る3階席との音響の違いに驚く・・・
まず、真ん前にもかかわらず、ヴィオラの音が聴き取りにくい。ヴィオラのサウンド・ポートはP席側(舞台後ろ)を向いているからなのだろう・・・むしろ、指揮者の向こう側のヴァイオリン・セクションの音の方がよく聴き取れる程だ・・・
3階席では、コンサート・ホールという拡散音場で程良くブレンドされた音として聴いているが、舞台真ん前はブレンドされる前の音として(表現は悪いが)バラバラな音(分離された音と言うべきか?)として聴こえる。
各楽器からの距離差がタイミングのズレとして明確に認識出来るのだ・・・先週のマーラー8番、舞台と客席バンダの音のタイミング・ズレと同様、聴く場所によって「音のアタマのタイミング」がずれる・・・
音速360m/secという物理現象・・・36mの距離で0.1秒の差が生じるのだから無視出来ないファクターだ・・・舞台から距離を置く程に音の頭のタイミング差は小さくなる(無限遠ならゼロとなる)・・・ホールのどの客席で響く音を想定して音のバランスやタイミングを調整するのか、一度指揮者に聞いてみたいものだ・・・・
ま、それはさておき、やはりベートーヴェンの「田園」は名曲だなあ・・・リピート無しでほっとしたし、舞台近くで雄弁に語りかけるバスの音がよく聴き取れて、改めて田園という曲の凄さを認識した・・・今度スコア片手に聴こうかな・・・期待?したマエストロ・コバケンの唸り声は今回は何故か皆無であった・・・う~ん・・・
アンコールは「定番」のダニー・ボーイ(弦楽合奏版)・・・やはり、これを聴かないとね・・・
コバケン・スペシャルはこれでお終いだが、来年はマーラーの3番を振るそうな・・・期待しようじゃないか・・・んでは。
まず、真ん前にもかかわらず、ヴィオラの音が聴き取りにくい。ヴィオラのサウンド・ポートはP席側(舞台後ろ)を向いているからなのだろう・・・むしろ、指揮者の向こう側のヴァイオリン・セクションの音の方がよく聴き取れる程だ・・・
3階席では、コンサート・ホールという拡散音場で程良くブレンドされた音として聴いているが、舞台真ん前はブレンドされる前の音として(表現は悪いが)バラバラな音(分離された音と言うべきか?)として聴こえる。
各楽器からの距離差がタイミングのズレとして明確に認識出来るのだ・・・先週のマーラー8番、舞台と客席バンダの音のタイミング・ズレと同様、聴く場所によって「音のアタマのタイミング」がずれる・・・
音速360m/secという物理現象・・・36mの距離で0.1秒の差が生じるのだから無視出来ないファクターだ・・・舞台から距離を置く程に音の頭のタイミング差は小さくなる(無限遠ならゼロとなる)・・・ホールのどの客席で響く音を想定して音のバランスやタイミングを調整するのか、一度指揮者に聞いてみたいものだ・・・・
ま、それはさておき、やはりベートーヴェンの「田園」は名曲だなあ・・・リピート無しでほっとしたし、舞台近くで雄弁に語りかけるバスの音がよく聴き取れて、改めて田園という曲の凄さを認識した・・・今度スコア片手に聴こうかな・・・期待?したマエストロ・コバケンの唸り声は今回は何故か皆無であった・・・う~ん・・・
アンコールは「定番」のダニー・ボーイ(弦楽合奏版)・・・やはり、これを聴かないとね・・・
コバケン・スペシャルはこれでお終いだが、来年はマーラーの3番を振るそうな・・・期待しようじゃないか・・・んでは。
2012年7月16日(月) 名古屋マーラー音楽祭 マーラー交響曲第8番 2日目 ― 2012年07月20日 07時45分
開演前・・・デジカメで・・・
開演前・・・こちらは携帯カメラで・・・こっちのほうが写りが良い・・・
合唱団登場・・・
終演後の様子・・・字幕ボードに
Herzlich Danke
♥Gustav und Alma♥
の文字が・・・
Herzlich Danke
♥Gustav und Alma♥
の文字が・・・
写真では区別しにくいですが、合唱団のパート区分がTシャツの色と対応しているそうな・・・視覚的にも気を配ってるんですなあ・・・
マーラーの交響曲第8番、こりゃ、語り無しの宗教曲だと実感した・・・この曲を交響曲というフォルム・形式で解析しようとしても意味が無いだろう・・・んじゃ、なんで「交響曲」として発表したか・・・ま、それを肴にスコアを眺めながらまた聴くことにしよう・・・お疲れ様でした。
名古屋マーラー音楽祭 マーラー交響曲第8番 1日目 ― 2012年07月16日 10時20分
昨日、2012年7月15日(日) No Nukes! NAGOYAデモ(ツイッター)第2回!の後、名古屋マーラー音楽祭(ツイッター) 交響曲第8番演奏会1日目を聴いてきました・・・実は、名古屋マーラー音楽祭を聴くのはこれが最初なのだ・・・で、明日が最後・・・
演奏者が載る前のステージ・・・5階席から・・・

終演後、マエストロのお声がけで写真撮影解禁され、これまでのマーラー音楽祭の出演者紹介・・・
記念撮影まで・・・
今日も聴くのだ・・・やはり、マーラーの8番は「宇宙の鳴動」ですな・・・んでは。
今日も聴くのだ・・・やはり、マーラーの8番は「宇宙の鳴動」ですな・・・んでは。
名フィル クリスマス・ポップスコンサート2011 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月15日(木) ― 2011年12月31日 10時40分
ここ数年ご無沙汰していた、名フィルのクリスマス・ポップス・コンサートを聴きました。
名フィル クリスマス・ポップス・コンサート 2011
愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール
2011年12月15日(木)
ボブ佐久間 指揮 名フィル・ポップスオーケストラ
アンダーソン: そりすべり
ボブ佐久間編: 神様がスイングしたら…
(神の御子は今宵しも/スイング版)
ボブ佐久間編: クリスマス・キャロル・メドレー
ボブ佐久間編: クリスマス! クリスマス!! クリスマス!!!
ボブ佐久間編: ラヴ・アット・ザ・ムーヴィーズVol.3
~映画音楽の巨匠~
名フィル クリスマス・ポップス・コンサート 2011
愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール
2011年12月15日(木)
ボブ佐久間 指揮 名フィル・ポップスオーケストラ
アンダーソン: そりすべり
ボブ佐久間編: 神様がスイングしたら…
(神の御子は今宵しも/スイング版)
ボブ佐久間編: クリスマス・キャロル・メドレー
ボブ佐久間編: クリスマス! クリスマス!! クリスマス!!!
ボブ佐久間編: ラヴ・アット・ザ・ムーヴィーズVol.3
~映画音楽の巨匠~
クリスマス&映画音楽好きの俺にとっては至福の時間であった・・・ボブ佐久間氏のとぼけた語りも相変わらずであった・・・これが今年のコンサートの聴き納めとなった・・・な?
セントラル愛知交響楽団「市民合唱団による悠久の第九」 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月14日 (水) ― 2011年12月30日 18時00分
毎年恒例のヤツですな・・・
・・・ということで、1部の演奏中は、ロビーに展示されていた、日本国際飢餓対策機構・中京医薬品の置き薬箱他の展示を見る・・・
指揮/齊藤一郎、セントラル愛知交響楽団
1部 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番
ピアノ:牧村沙保
2部 悠久の第九
ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」
ソプラノ/森本典子 アルト/谷田育代
テノール/中井亮一 バリトン/木村聡
合唱/悠久の第九合唱団
2011年12月14日(水)
愛知県芸術劇場コンサートホール にて
今回、のんびりし過ぎて、第1部は聴き損ねてしまったのだが・・・1部 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番
ピアノ:牧村沙保
2部 悠久の第九
ベートーヴェン:交響曲第9番 ニ短調 作品125 「合唱付」
ソプラノ/森本典子 アルト/谷田育代
テノール/中井亮一 バリトン/木村聡
合唱/悠久の第九合唱団
2011年12月14日(水)
愛知県芸術劇場コンサートホール にて
・・・ということで、1部の演奏中は、ロビーに展示されていた、日本国際飢餓対策機構・中京医薬品の置き薬箱他の展示を見る・・・
あんまり見る人がいなかったのだろうか・・・綺麗な解説員(と思うが)のおねーさんが懇切丁寧に熱意を持って説明してくれた・・・これだけでもこの演奏会に来た甲斐があった(←オイオイ)
ま、それはともかく、今回の第9、実に見透しのいい演奏で、「第9ってこんなに短い曲だった?」という印象であった・・・なかなか良かったでっせ・・・んでは。
名フィル第386回定期「愛の死」~「愛と死」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年12月3日(土) ― 2011年12月06日 06時20分
疲れていたのか、夢うつつで聴いていて、シートでアタマが左右にふ~らふら・・・お隣の席の方、ごめんなさい・・・たぶんイビキはかいてなかったと思うけど・・・どちらの音楽も眠りを誘うのだ・・・
ヴァイオリンの両翼配置とコントラバス・セクションを舞台左側に配置しているのは指揮者の好みだそうな・・・普段の配置と異なるせいか、響きも違って聞こえたような・・・視覚の影響も大きいけどね・・・
なかなかいい演奏だった。特にブルックナーは時折オルガンのように響くブラスが心地よい・・・
残念だったのは少々フライング気味の拍手。こういう曲は指揮者の肩の力が抜けたのを見計らって拍手してくれると嬉しい。拍手のスタートを競ってもしょうがないので、こういう曲の拍手は落ち着いてゆっくりとやってほしいものだが・・・んでは。
ヴァイオリンの両翼配置とコントラバス・セクションを舞台左側に配置しているのは指揮者の好みだそうな・・・普段の配置と異なるせいか、響きも違って聞こえたような・・・視覚の影響も大きいけどね・・・
なかなかいい演奏だった。特にブルックナーは時折オルガンのように響くブラスが心地よい・・・
残念だったのは少々フライング気味の拍手。こういう曲は指揮者の肩の力が抜けたのを見計らって拍手してくれると嬉しい。拍手のスタートを競ってもしょうがないので、こういう曲の拍手は落ち着いてゆっくりとやってほしいものだが・・・んでは。
名フィル第385回定期演奏会「愛の渇望」~「愛と死」シリーズ~ 愛知県芸術劇場コンサートホール 2011年11月18日(金) ― 2011年11月20日 11時05分
ムソルグスキー[ショスタコーヴィチ編]:
歌劇『ホヴァンシチナ』前奏曲(モスクワ河の夜明け)
ショスタコーヴィチ: ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 作品77*
コダーイ: 組曲『ハーリ・ヤーノシュ』 作品35a**
バルトーク:バレエ『中国の不思議な役人(不思議なマンダリン)』 作品19,Sz.73 組曲
ゴロー・ベルク(Golo Berg 指揮)
アリーナ・イブラギモヴァ*(Alina Ibragimova ヴァイオリン)
崎村潤子**(ツィンバロン)
金曜日は雨が降りそうだったけど、まあ持ちこたえた・・・かな。23時くらいに雨がパラパラと・・・昨日は土砂降り・・・土曜定期はお客さんどうだったろう・・・濃いプロだったからねえ。
今回のプロはレコードでは聴けるが実演では滅多に聴けない曲ばかり。ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲、ショスタコーヴィチは苦手(あのひねくれたメロディーがどうにも理解出来ん・・・)なんだけど、今回の演奏、Alina Ibragimova の熱演には圧倒された。彼女は明日月曜日、宗次ホールでバッハを弾くそうだ。行こうかな?ちなみに金曜日はアンコールにバッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 BWV.1004より第3曲「サラバンド」を弾いてくれた。
コダーイの『ハーリ・ヤーノシュ』組曲。ツィンバロンは音が小さいので、オケとのバランスを取るのに苦労したのではないだろうか?舞台から離れた3階席では聴き取りづらかった・・・まあ、でも実演で聴けて良かった。
バルトークの「中国の不思議な役人」も正直苦手な曲だが、こうして実演で聴くとなんとなく「凄い曲だ」ということは分かる。曲が終わってからの拍手がまばらだったのは、曲よく知らない観客が多いからかな?俺もよく知らなかったしね。
今回のプログラム冊子に来シーズンのプログラム発表が載っていた。来シーズンは期待出来るかな・・・
愛知県芸術文化センターの夜の風景・・・
愛知県美術館で開催される生誕100年 ジャクソン・ポロック展のPRのようだ・・・
歌劇『ホヴァンシチナ』前奏曲(モスクワ河の夜明け)
ショスタコーヴィチ: ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 作品77*
コダーイ: 組曲『ハーリ・ヤーノシュ』 作品35a**
バルトーク:バレエ『中国の不思議な役人(不思議なマンダリン)』 作品19,Sz.73 組曲
ゴロー・ベルク(Golo Berg 指揮)
アリーナ・イブラギモヴァ*(Alina Ibragimova ヴァイオリン)
崎村潤子**(ツィンバロン)
金曜日は雨が降りそうだったけど、まあ持ちこたえた・・・かな。23時くらいに雨がパラパラと・・・昨日は土砂降り・・・土曜定期はお客さんどうだったろう・・・濃いプロだったからねえ。
今回のプロはレコードでは聴けるが実演では滅多に聴けない曲ばかり。ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲、ショスタコーヴィチは苦手(あのひねくれたメロディーがどうにも理解出来ん・・・)なんだけど、今回の演奏、Alina Ibragimova の熱演には圧倒された。彼女は明日月曜日、宗次ホールでバッハを弾くそうだ。行こうかな?ちなみに金曜日はアンコールにバッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調 BWV.1004より第3曲「サラバンド」を弾いてくれた。
コダーイの『ハーリ・ヤーノシュ』組曲。ツィンバロンは音が小さいので、オケとのバランスを取るのに苦労したのではないだろうか?舞台から離れた3階席では聴き取りづらかった・・・まあ、でも実演で聴けて良かった。
バルトークの「中国の不思議な役人」も正直苦手な曲だが、こうして実演で聴くとなんとなく「凄い曲だ」ということは分かる。曲が終わってからの拍手がまばらだったのは、曲よく知らない観客が多いからかな?俺もよく知らなかったしね。
今回のプログラム冊子に来シーズンのプログラム発表が載っていた。来シーズンは期待出来るかな・・・
愛知県芸術文化センターの夜の風景・・・
愛知県美術館で開催される生誕100年 ジャクソン・ポロック展のPRのようだ・・・
・・・んでは。
Sydney Symphony Orchestra/Vladimir Ashkenazy 名古屋公演 2011年11月9日(水) 愛知県芸術文化センター コンサートホールにて ― 2011年11月12日 15時00分
Sydney Symphony Japan and Korea Tour 2011
Sydney Symphony Orchestra
Vladimir Ashkenazy Principal Conductor & Artistic Advisor
愛知県芸術文化センター 芸術劇場 コンサートホール
2011年11月9日 名古屋公演
Beethoven
Overture from "Die Geschöpfe des Prometheus"
Violin Concerto in D major,Op.61
violin : 庄司紗矢香
Rachmaninov : Symphony no.2
久しぶりに海外のオーケストラを聴きました。やはり音が綺麗で大きいのはいいね・・・。
前半の「プロメテウスの創造物」序曲とヴァイオリン協奏曲は初めて聴く曲。ヴァイオリン協奏曲はティンパニから始まる・・・くらいしか知らなかったが、中盤以降は聴いた記憶があるメロディーが・・・ガタイの大きい団員の中でソロ・ヴァイオリニストの小ささが際立つ・・・
後半のラフマニノフ、若手が多い?せいかアンサンブルが少々粗いけど、いいラフマニノフでした。
ラフマニノフの後、アンコールのリクエストがあったけど、流石にそれには応えずにコンサート・マスターが指揮者を引っ張ってステージ袖に退散してくれて良かった・・・ラフマニノフの後でアンコールは聴きたくないよ・・・
演奏会が終わった後、シドニー響の団員と道路で遭遇、その後腹が減ったので、沖縄居酒屋ゆいゆい へ・・・
んでは。



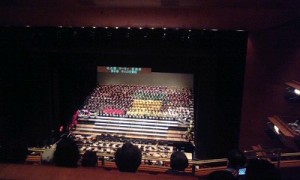


















最近のコメント